2012年8月11日土曜日
P.S. don’t get bought by Amazon.なSSD Nodesに興味あり。
今回は、クラウド情報です。
SSD Nodesの人からメールが来て、気になって調べて読んだ記事。
Amazon AWS vs SSDNotes – SSD Nodes Rocks
AWS RDS => 3min 15sec
SSD Lepton => 0.024sec
え?! マジですか。All SSDのHaasですが、ここまで差がでるのかなぁ〜。
SSDとioDriveの比較記事は以前に読みましたが、AWSと他の比較事例はあまり調べてなかった。
サービスメニューですが、
Laptonは、4×3.4GHz 8GB SSDをOS・データ領域に選べて$69.99 Fixed Monthly。
Micro Node のTauは、$17.99 Fixed Monthly。
で、記事の中にある文章を引用。
>SSD Nodes allowed us to essentially run queries in 1/100th of the time of that which they were running on AWS.
...
>P.S. don’t get bought by Amazon.
そりゃ、100倍のパフォーマンスを得れば、そう書きたくなるわ。
ということで、メールに『マジですごいね』って返信したら、
SSD Nodes Founder のMatt Conner氏から即レスがきて、引き続き色々と質問中。
All SSDのHaas、面白そうです。
2012年8月5日日曜日
LL decadeに行って思うこれからの10年
LL decadeに行ってきたよ。
以下のTweetで、会場の空気を掴んでみてね。
「LL Decadeのツイート」をトゥギャりました。@mad_p
LL decade のプログラミング言語処理系を自作してわかったこと & 俺たちの継続的hogehogeは始まったばかりだ!のまとめ: @rmacchoj7
Perl、PHP、Python、Rubyと4言語の重鎮が集まっての講演、言語開発者同士の質疑応答、そしてLTと濃〜い内容のイベント。
 ■PHPが自虐的www
■PHPが自虐的www基調講演でのスーパーギーク miyagawaさん
「転職する時にPHPやってる会社は最初から候補にいれない。DISじゃなく自分がやりたくないだけ。」
PHPエンジニア、高齢化の流れは避けられそうにないねw。4言語ごとに仕事で使ってる年代層を調べたら、確実にPHPが上にいるだろうなぁ〜。PHPはレガシーコードとして、臭いものには蓋をしろ的扱いにされそうだwww
個人的には、これからの10年は、JavaScriptが益々話題豊富で活性化して欲しいと思っているのと、Rubyが2013年2月に2.0をリリースすることで、またRails絡みのアップデートが熱いだろうと。10年もかからない間に、JavaScriptの元でデザイナーとフロントエンジニアのスキルが統合されて、WebCreatorとして深く活躍できる人材がもっと出て欲しいと期待。Ruby人気は・・・止まらなそうだねw
■クラウドワーク
 Shibuya.jsの@takesakoさんのLTでちょっと触れた、シリコンバレーでのクラウドワークが盛り上がりなところが響いた。日本でもクラウドワークス、ランサーズとサービスが盛り上がり初めていますからねぇ〜。プロとしてのソロエンジニア、プロジェクトオーナーとしての企業、企業につとめるエンジニアチーム、その関係も10年で大きく変化しそうですね〜。外注・内製にこだわらず、『いいものを作る』ということをどんな形で実現するかですね。
Shibuya.jsの@takesakoさんのLTでちょっと触れた、シリコンバレーでのクラウドワークが盛り上がりなところが響いた。日本でもクラウドワークス、ランサーズとサービスが盛り上がり初めていますからねぇ〜。プロとしてのソロエンジニア、プロジェクトオーナーとしての企業、企業につとめるエンジニアチーム、その関係も10年で大きく変化しそうですね〜。外注・内製にこだわらず、『いいものを作る』ということをどんな形で実現するかですね。ということで、これからの10年、益々プログラミングを楽しんでいける世の中になりそうです。
2012年8月2日木曜日
エンジニアの成長
α版は、私がインフラ・ミドルウェア・アーキテクチャ等々を設計(一部実装w)して、チームに開発してもらったのですが、β'は数週間前の時点で設計はなかったわけで(^^;
 調査・設計からすべてお願いして実現したのです。私は、機能の要求事項とアーキテクチャの要点をアドバイスすることに終始。
調査・設計からすべてお願いして実現したのです。私は、機能の要求事項とアーキテクチャの要点をアドバイスすることに終始。DB,NoSQL,API,IndexEngine等々、未経験なことを短期間で実現する成長スピードはすごいですね。経済成長の数字よりも、およそ人の成長の方がすごいです。
 中心メンバーは、当たり前ですが私より10歳以上は年下。まぁ、あっという間に吸収して抜かれて行きますね。今後が楽しみです。そして、それは強烈なインパクトになるでしょう。
中心メンバーは、当たり前ですが私より10歳以上は年下。まぁ、あっという間に吸収して抜かれて行きますね。今後が楽しみです。そして、それは強烈なインパクトになるでしょう。日本のWeb系エンジニアの皆さんは、戦略立てて、ポジション・ブランドをセルフマネジメントしないと。ジョブズが講演したように、『古きものを消し去り、新しきものへの道をつくりだす』で、一気に波にのまれちゃいますね。
仕事しながら、そんなことを感じちゃいました。大きな変化の中にいる感じがして、面白い時代だと思います(笑)
2012年5月26日土曜日
Webアプリ開発を楽しんで学ぶ場をつくります
Webアプリケーションをもっと楽しんで作る人を増やすための場を作ります。
Webアプリケーションは、誰でも学ぶことで作ることが可能です。Webを通じて、自分のアイデア、創造性をもっと発揮することができます。
労働ではなく、芸術を楽しみたいと思いませんか?世の中にあるものを、もっと素晴らしいものへ作りなおしてみたくないですか?でも、スキルがない、知識がない。それで諦めたり、もどかしい思いをするのはもったいないです。
僭越ながら、そんな方々がWebを通じて表現できるようになることをお手伝いさせて頂きます。
Web Creation Fun Club
と名付けたグループを作りました。エンジニア・デザイナーが本業ではない方でも、Webアプリケーションを作ってみたいと思う方へ、Webアプリケーションに関わる知識・スキルを学べる場を提供します。
まだ、活動の全体像をこれから作る感じではありますが、6月30日(土)に、都内で第一回目の勉強会を実施する予定です。超入門からはじめて、まずは開発環境作りからになるかと思いますが、興味のある方、連絡おまちしております。勉強会の参加費用は、300円〜500円です。
より多くの方が、Webの世界を楽しむために。
Twitter:@rmacchoj7
Facebook:Takashi Asanuma
Webアプリケーションは、誰でも学ぶことで作ることが可能です。Webを通じて、自分のアイデア、創造性をもっと発揮することができます。
労働ではなく、芸術を楽しみたいと思いませんか?世の中にあるものを、もっと素晴らしいものへ作りなおしてみたくないですか?でも、スキルがない、知識がない。それで諦めたり、もどかしい思いをするのはもったいないです。
僭越ながら、そんな方々がWebを通じて表現できるようになることをお手伝いさせて頂きます。
Web Creation Fun Club
と名付けたグループを作りました。エンジニア・デザイナーが本業ではない方でも、Webアプリケーションを作ってみたいと思う方へ、Webアプリケーションに関わる知識・スキルを学べる場を提供します。
まだ、活動の全体像をこれから作る感じではありますが、6月30日(土)に、都内で第一回目の勉強会を実施する予定です。超入門からはじめて、まずは開発環境作りからになるかと思いますが、興味のある方、連絡おまちしております。勉強会の参加費用は、300円〜500円です。
より多くの方が、Webの世界を楽しむために。
Twitter:@rmacchoj7
Facebook:Takashi Asanuma
2012年5月10日木曜日
Wordpressあります
Wordpressを使い始めたいけど、何から用意していいか分からない、または、Wrodpress を使い始められるか、まずは触って確かめたいって方いらっしゃいませんか?
そんな方向けに、私の持っているサーバからWordpressをお試しで使える環境を無償で提供しています。ご希望の方ごとに、サンプル環境を構築して、Wordpressの投稿・管理機能をお渡しします。今のところ、私とFacebookでリアルでのつながりがある方、または、つながっているお友達からの紹介の方に提供します。
Wordpressサンプル
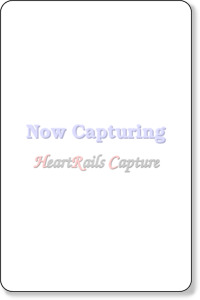
こんなことを開始したのも、ネットの業界に携わるシステムエンジニアとして、より多くの皆さんにインターネット上での情報発信、コンテンツ作りを身近にしたいという想いがあり始めました。
ある程度の知識がある方は、自分のドメインを持って、フリーウェアのブログなどを構築し、自分の生活・ビジネス・ブランディングにネットを活用しています。
ただ、『ある程度の知識』の壁を感じて、なかなか踏み出せない方が多いのも事実ではないでしょうか?
システムエンジニアの役割は、システムを難しくしないで、簡単・便利・速くすることが使命だと思うのです。ソーシャルメディアを始め、インターネット上での情報交流は、思わぬものを生み出す可能性に溢れています。
そんな可能性の中に、より多くの方が手軽に入って行けるように支援したいと思います。
なので、気軽にTwitter,Facebookのメッセージなどでご連絡ください。
他にも、独自ドメインで自分のサイトを持ちたいけどなにから用意したらいいって相談も歓迎です。
このブログを目にした方が、より良いネットワークを築けるよう願っています。
Twitter: @rmacchoj7
Facebook: Takashi Asanuma

そんな方向けに、私の持っているサーバからWordpressをお試しで使える環境を無償で提供しています。ご希望の方ごとに、サンプル環境を構築して、Wordpressの投稿・管理機能をお渡しします。今のところ、私とFacebookでリアルでのつながりがある方、または、つながっているお友達からの紹介の方に提供します。
Wordpressサンプル
こんなことを開始したのも、ネットの業界に携わるシステムエンジニアとして、より多くの皆さんにインターネット上での情報発信、コンテンツ作りを身近にしたいという想いがあり始めました。
ある程度の知識がある方は、自分のドメインを持って、フリーウェアのブログなどを構築し、自分の生活・ビジネス・ブランディングにネットを活用しています。
ただ、『ある程度の知識』の壁を感じて、なかなか踏み出せない方が多いのも事実ではないでしょうか?
システムエンジニアの役割は、システムを難しくしないで、簡単・便利・速くすることが使命だと思うのです。ソーシャルメディアを始め、インターネット上での情報交流は、思わぬものを生み出す可能性に溢れています。
そんな可能性の中に、より多くの方が手軽に入って行けるように支援したいと思います。
なので、気軽にTwitter,Facebookのメッセージなどでご連絡ください。
他にも、独自ドメインで自分のサイトを持ちたいけどなにから用意したらいいって相談も歓迎です。
このブログを目にした方が、より良いネットワークを築けるよう願っています。
Twitter: @rmacchoj7
Facebook: Takashi Asanuma

2012年3月10日土曜日
インフラエンジニアとロールケーキ
今回は、非常に趣味的な話です。私が、なぜロールケーキを作るのが好きなのか?
最近になって自分でも理解したことなのですが、ロールケーキとインフラエンジニアとのつながりについて、つらつらと書いてみたいと思います。
私の思うロールケーキの『美の壺』三点とインフラエンジニアのつながりについて。
1.カットしたときの丸い形
2.シンプルだが隠れた技術
3.なんといっても生地が主役
■カットしたときの丸い形
とにかく、あのカットした断面の美しさが好きです(笑。 カットされた時の『の』の字型に惹かれます。普通のケーキだと、デコレートされた表の姿に目が行きますが、ロールケーキの場合、カットした時の姿に目が行きます。このカットした時の隠れた『美』に惹かれます。Webのインフラも、全体の姿だけでなく、各機能ごとの『断面』を見ても美しくありたいものです。上手く設計できたシステムは、どこをカットしてもシステムの姿を保ち、全体の機能を保つように設計され、堅牢性・応答性・可用性を保ちます。システムの中・断面を見た時に、誰もが息を呑む、そんな美のあるシステムを構築したいものです。

■シンプルだが隠れた技術
ロールケーキを焼けると言うと、巻くのが難しいでしょう?と言われます。ですが、巻くこと自体は、そんなに難しくないのです。巻くことを可能にするのは、生地を作る段階での工夫にあるのです。生地を作る段階に配合する卵と薄力粉のバランスで生地の厚みと柔軟性が決まります。薄力粉が多い場合は、厚みのある生地が焼けますが、反面、生地が硬くなり巻き難くなります。逆に、少なければ柔らかくなり巻きやすいですが、生地が薄くなりクレープに近くなります。このシンプルだけど奥が深いバランスを作る技術が『美』です。ケーキ全体を支える生地は、インフラシステムそのものです。インフラ構築におけるさじ加減で、システム全体の厚み・柔軟性が決まります。巻くときにわかる生地に込められた技術。ここに『美』を感じずにはいられません。インフラにおいてもシステム全体を巻くために、日夜、努力と技術を注ぎ込み、全体をまとめるだけの柔軟で厚みのあるインフラの提供を心がけたいものです。

■なんといっても生地が主役
ここが一番のポイントです。普通のケーキでは、クリームやフルーツなどのデコレートにより目に見えないことの多い生地ですが、ロールケーキでは、普段は隠れた存在の生地が表面に来て、主役の座となっているのです!ここが『美』のポイントです。インフラの仕事は、とかく表面に現れず、あるのが当たり前の仕事です。よくランチでも、『インフラってどんな仕事ですか?イメージできません。』と言われます。しかし、ロールケーキのように、普段は隠れた存在のインフラでも、主役のごとく人・世の中を楽しませることができるのです。工夫しだいで資源を無駄なく利用し、社会にも自然にも貢献できます。まるっと世の中を包み込むような、そんなインフラを作りたいものです。
以上、ロールケーキ作りに感じるインフラエンジニアの職人気質です。一本焼くと10人くらいで分けて食べれるのもいいですね。ロールケーキもインフラも、自分の職人気質を表現する大事な場所です。皆さんにも、芸術性・職人気質を表現する場所が各々あると思います。お互い、その場所を分かち合い・シェアすることで繋がり、より良い社会作りをして行きましょう。
ロールケーキあり、故に職人たる我あり。

最近になって自分でも理解したことなのですが、ロールケーキとインフラエンジニアとのつながりについて、つらつらと書いてみたいと思います。
私の思うロールケーキの『美の壺』三点とインフラエンジニアのつながりについて。
1.カットしたときの丸い形
2.シンプルだが隠れた技術
3.なんといっても生地が主役
■カットしたときの丸い形
とにかく、あのカットした断面の美しさが好きです(笑。 カットされた時の『の』の字型に惹かれます。普通のケーキだと、デコレートされた表の姿に目が行きますが、ロールケーキの場合、カットした時の姿に目が行きます。このカットした時の隠れた『美』に惹かれます。Webのインフラも、全体の姿だけでなく、各機能ごとの『断面』を見ても美しくありたいものです。上手く設計できたシステムは、どこをカットしてもシステムの姿を保ち、全体の機能を保つように設計され、堅牢性・応答性・可用性を保ちます。システムの中・断面を見た時に、誰もが息を呑む、そんな美のあるシステムを構築したいものです。

■シンプルだが隠れた技術
ロールケーキを焼けると言うと、巻くのが難しいでしょう?と言われます。ですが、巻くこと自体は、そんなに難しくないのです。巻くことを可能にするのは、生地を作る段階での工夫にあるのです。生地を作る段階に配合する卵と薄力粉のバランスで生地の厚みと柔軟性が決まります。薄力粉が多い場合は、厚みのある生地が焼けますが、反面、生地が硬くなり巻き難くなります。逆に、少なければ柔らかくなり巻きやすいですが、生地が薄くなりクレープに近くなります。このシンプルだけど奥が深いバランスを作る技術が『美』です。ケーキ全体を支える生地は、インフラシステムそのものです。インフラ構築におけるさじ加減で、システム全体の厚み・柔軟性が決まります。巻くときにわかる生地に込められた技術。ここに『美』を感じずにはいられません。インフラにおいてもシステム全体を巻くために、日夜、努力と技術を注ぎ込み、全体をまとめるだけの柔軟で厚みのあるインフラの提供を心がけたいものです。

■なんといっても生地が主役
ここが一番のポイントです。普通のケーキでは、クリームやフルーツなどのデコレートにより目に見えないことの多い生地ですが、ロールケーキでは、普段は隠れた存在の生地が表面に来て、主役の座となっているのです!ここが『美』のポイントです。インフラの仕事は、とかく表面に現れず、あるのが当たり前の仕事です。よくランチでも、『インフラってどんな仕事ですか?イメージできません。』と言われます。しかし、ロールケーキのように、普段は隠れた存在のインフラでも、主役のごとく人・世の中を楽しませることができるのです。工夫しだいで資源を無駄なく利用し、社会にも自然にも貢献できます。まるっと世の中を包み込むような、そんなインフラを作りたいものです。
以上、ロールケーキ作りに感じるインフラエンジニアの職人気質です。一本焼くと10人くらいで分けて食べれるのもいいですね。ロールケーキもインフラも、自分の職人気質を表現する大事な場所です。皆さんにも、芸術性・職人気質を表現する場所が各々あると思います。お互い、その場所を分かち合い・シェアすることで繋がり、より良い社会作りをして行きましょう。
ロールケーキあり、故に職人たる我あり。

2012年3月3日土曜日
インフラエンジニアとシブヤ朝そうじ
今朝は、シブヤ朝そうじに参加して来ました。今年から参加を始めて、3回目になります。
朝そうじをしながら、これもインフラエンジニアの仕事と同じだなぁ〜と感じたことをつらつらと書きます。
毎月第一土曜日の朝に、Twitter,Facebook上で知り合った方々のご縁で、渋谷のゴミ拾いをしています。特別に義務感や目標があって拾っている訳でもなく、ふらっと集まっては道にあるゴミを自然と拾っていくだけです。
私の仕事的にも、月初はシステムの掃除をしてたりします。古いログやバックアップデータのアーカイブを削除したり、データベースの過去データを掃除したり。
システム上でサービスが動き続ける限り、システム上の何かしらの資源(例えばハードディスクなど)を使い続けます。システムの掃除をしないとどうなるかというと、どんなコンピュータ、ネットワークと言えども資源的には有限なので、どこかの時期で必ず上限値に到達し、すべての資源を使い切ってしまいます。なので、上限値を越えないように、定期的にチェックして、削除できるものは削除して、増やすべきものは増やし、資源を保つように運用する訳です。このように、インフラエンジニアの仕事の一面は、資源監督・管理にあると言えます。上司から最初にミッションとして教え込まれたのも、この役割の徹底です。
そこで思うのは、ゴミを拾うのもログ等のデータ削除も、同じように資源監督の意味で同じだと感じています。社会のシステムが動きつづける限り、何かしらの資源を使った跡が残って行く訳です。その資源を保つ仕組みも自然と働く訳です。ただ、あまりに巨大な資源を使うと、用意に削除(またはバックアップ等の保全)できなくなるのも似ています。
コンピュータシステムでも、あまりに巨大するぎるデータが急増したりすると、資源の保全難易度は急速に高まります。削除にあまりに時間・リスクが高くなり、削除の負荷でシステムを稼働した状態を保てない場合もあります。ゴミも急速に拡大すると処分自体が、抱えきれない負荷を生み出すかもしれません。コンピュータシステムも社会も、有限な資源に目を向けて無駄な消費の無いように心がけたいものです。
ゴミあり、故にゴミを拾う我あり。

朝そうじをしながら、これもインフラエンジニアの仕事と同じだなぁ〜と感じたことをつらつらと書きます。
毎月第一土曜日の朝に、Twitter,Facebook上で知り合った方々のご縁で、渋谷のゴミ拾いをしています。特別に義務感や目標があって拾っている訳でもなく、ふらっと集まっては道にあるゴミを自然と拾っていくだけです。
私の仕事的にも、月初はシステムの掃除をしてたりします。古いログやバックアップデータのアーカイブを削除したり、データベースの過去データを掃除したり。
システム上でサービスが動き続ける限り、システム上の何かしらの資源(例えばハードディスクなど)を使い続けます。システムの掃除をしないとどうなるかというと、どんなコンピュータ、ネットワークと言えども資源的には有限なので、どこかの時期で必ず上限値に到達し、すべての資源を使い切ってしまいます。なので、上限値を越えないように、定期的にチェックして、削除できるものは削除して、増やすべきものは増やし、資源を保つように運用する訳です。このように、インフラエンジニアの仕事の一面は、資源監督・管理にあると言えます。上司から最初にミッションとして教え込まれたのも、この役割の徹底です。
そこで思うのは、ゴミを拾うのもログ等のデータ削除も、同じように資源監督の意味で同じだと感じています。社会のシステムが動きつづける限り、何かしらの資源を使った跡が残って行く訳です。その資源を保つ仕組みも自然と働く訳です。ただ、あまりに巨大な資源を使うと、用意に削除(またはバックアップ等の保全)できなくなるのも似ています。
コンピュータシステムでも、あまりに巨大するぎるデータが急増したりすると、資源の保全難易度は急速に高まります。削除にあまりに時間・リスクが高くなり、削除の負荷でシステムを稼働した状態を保てない場合もあります。ゴミも急速に拡大すると処分自体が、抱えきれない負荷を生み出すかもしれません。コンピュータシステムも社会も、有限な資源に目を向けて無駄な消費の無いように心がけたいものです。
ゴミあり、故にゴミを拾う我あり。

登録:
投稿 (Atom)






